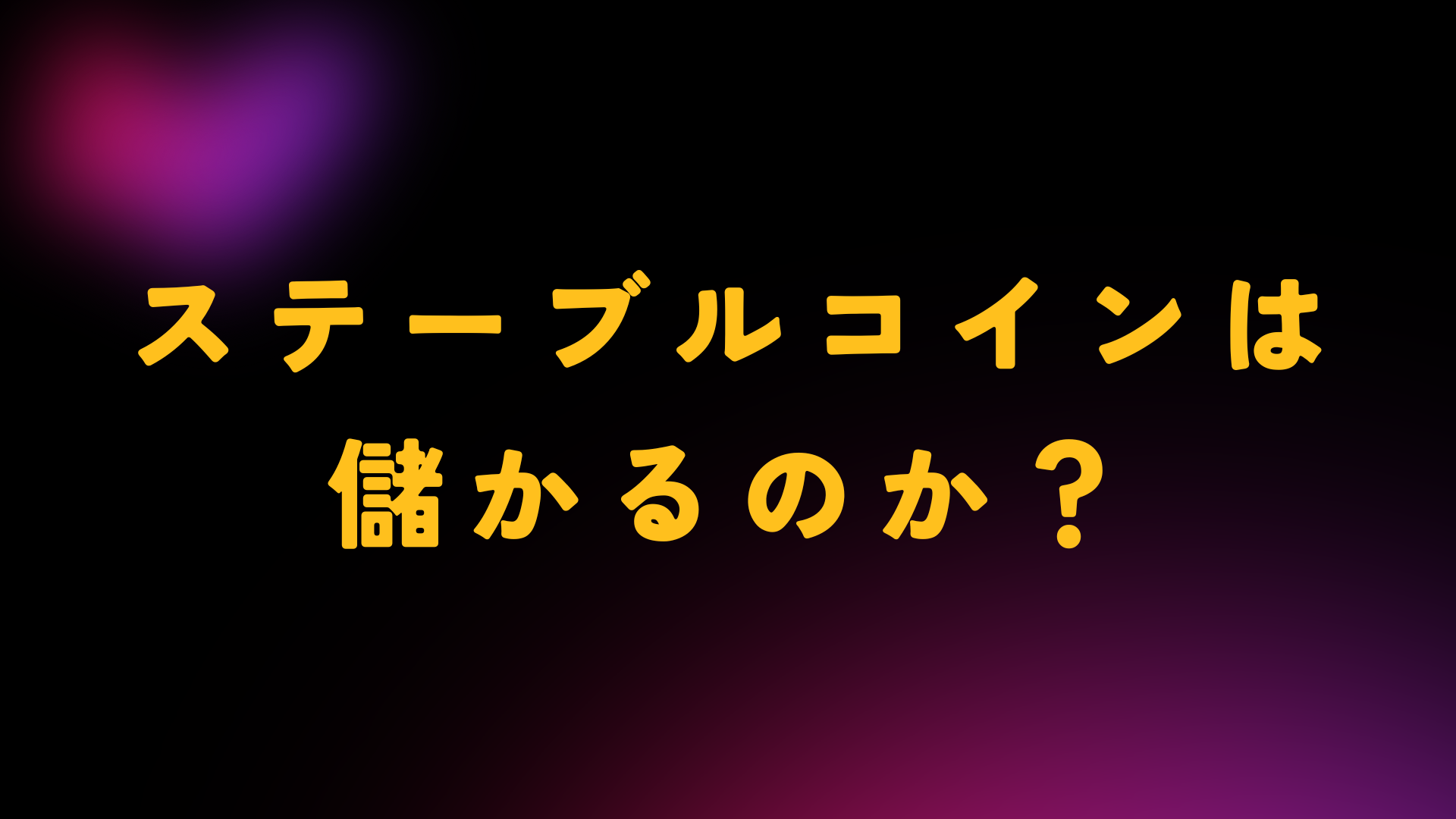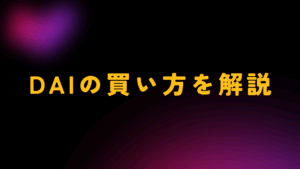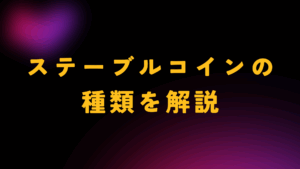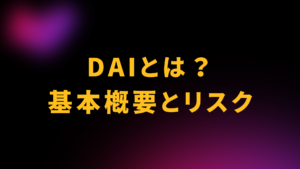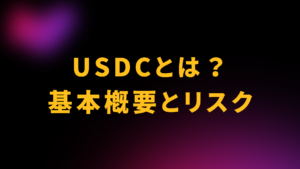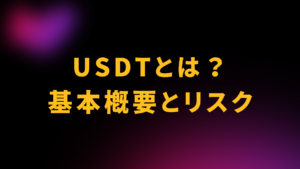投資対象としてのステーブルコインは「価格変動がほぼない暗号資産」という特性から、ビットコインのような値上がり益よりも運用収益を狙う商品として注目されています。
本記事では仕組み、安全性、収益化手段を体系的に整理し、日本国内の最新動向を踏まえて解説します。
ステーブルコインは儲かるのか?
ステーブルコインとは、ドルや円などの法定通貨と1対1で価値を保つことを目的とした暗号資産です。日本法では電子決済手段と呼ばれ、2023年施行の改正資金決済法で制度化されました。
まず、儲けるための前提として「価格が動かない資産から得られる利回りは何か」を整理しておきましょう。ステーブルコインでは値上がり益ではなく、貸付金利、流動性提供報酬、キャンペーン特典などが主な収益源となります。
同時に、利回りは裏付資産の運用利率やサービス提供会社の募集枠に依存します。したがって「価格変動リスクは小さいが、金利競争力がどこまで出るか」が収益性を評価する焦点です。
ステーブルコインの仕組みをわかりやすく解説
最初に押さえたいのは「1枚=1円(または1ドル)」がなぜ実現できるかという点です。
常に一定の価格になる仕組みには以下の3つがあります。
- 法定通貨建て資産担保型
- 暗号資産建て資産担保型
- アルゴリズム型
法定通貨建て資産担保型は、短期国債などの資産をステーブルコインと同じ額保有することによって、そのステーブルコインの価値を担保するものです。USDCやUSDTが該当します。
仮想通貨のUSDTとは?基本概要や他のステーブルコインとの違いを解説
仮想通貨のUSDCとは?基本概要や他のステーブルコインとの違いを解説
暗号資産建ては、短期国債などの昔からある資産ではなく、ビットコイン等の仮想通貨を保有してステーブルコインの価値を担保する方式です。DAIなどが該当します。
仮想通貨のDAIとは?基本概要や他のステーブルコインとの違いを解説
アルゴリズム型は、自動化された需給調整のプログラムで価格を維持します。ただしこの方式は暴落事例もあり、国内規制は厳格です。2022年の米TrraUSD事件が典型例で、価格崩壊が起きています。
日本で作られて発行されているステーブルコインの場合は、信託型と言い、これは週次の残高報告と監査が必須化されており、透明性が高い一方、運用範囲が国債中心のため高利回りは望みにくいというトレードオフがあります。
ステーブルコインの信用度は「裏付資産の質」「裏付資産の保管体制」「第三者監査」の三要素で測定できます。
ステーブルコインで儲ける運用方法3選
ステーブルコインは価格変動が小さいため、利回り追求型の運用と相性が良いです。ここでは日本在住者が比較的始めやすい3つの手法を紹介します。
- 国内レンディングサービス
- DeFiでのレンディング
- DeFiでの流動性提供
国内レンディングサービス
国内のレンディングサービスに預けることで、年利数%~10%程度の利回り収入を得られます。
レンディングサービスは国内取引所が運営しているサービスと、レンディング専門業者が運営しているサービスがあります。
各レンディングサービスの金利比較表は以下の記事で公開しています。
仮想通貨レンディングの金利一覧表を公開!業者選びのやり方がすべてわかる
レンディング専門業者の貸とくはステーブルコインの利回りが業界最高水準で、ステーブルコインを預けるだけで毎月11%の金利を獲得できます。
これらの運用方法の利回りの原資は取引所や業者の自己運用益や借手への再貸し付け金利に由来します。そのため、発行者信用リスクだけでなく取引所の信用リスクも負うことを忘れてはいけません。
DeFiでレンディング
AaveなどのレンディングプロトコルにUSDCを預け入れると、需要に応じて変動金利(年率1〜7%)が発生します。借手は同じプロトコル上で他資産を担保にステーブルコインを借入れ、レバレッジ取引やアービトラージに活用しています。
プロトコル破綻リスクはプール型より小さいものの、清算(担保売却)による損失が出るケースがあるため、プラットフォームの保険プールやセーフガード機能を確認しましょう。
Aaveではセーフティモジュールが導入されており、ある程度の損失補填が仕組まれています。
ガス代(Ethereum取引手数料)が高騰すると小口投資の利回りが相殺されてしまいますが、最近はそれらが起こらないLayer2への移行が進み、ArbitrumやOptimismではガス代が10分の1以下になる例も増えています。初期コストを抑えたい場合はL2ネットワークのAave等を利用するのが有利です。
DeFiで流動性提供
DeFi(分散型金融)とは、ブロックチェーン上で自動化された金融サービスの総称です。
UniswapやCurveなどの自動マーケットメイカーにステーブルコインを預け、取引手数料の一部を受け取ることで利回りを得ます。ステーブルコイン同士のペアは変動リスクが小さく、年率2〜8%程度が一般的です。
流動性提供(プール)には、プール全体の取引量低下による報酬減少やプール解散のリスクがあります。
さらに、スマートコントラクトの脆弱性から資金流出が起きる可能性も考慮しましょう。
保守的に運用したい場合は、複数プールに分散するか、預入期間を短めに設定するのが賢明です。
DeFiの利回りはオンチェーンでリアルタイム変動します。提供前にAPR(年率換算利回り)を確認し、見かけ上高い利回りでも一時的なキャンペーンで急低下するケースがあるため、取引履歴グラフをチェックする習慣が欠かせません。
ステーブルコインの購入方法
- 国内取引所の法定通貨ペア
- 海外取引所で購入してウォレットに送金
USDCを購入する方法で最も簡単なのは、SBI VCトレードでUSDCを日本円で直接買う方法です。
口座開設後、即時入金サービスを利用すれば数分で取引が完結します。手数料はスプレッド内包型で実質0.2〜0.4%が相場です。
海外取引所を経由する場合は、国内取引所でビットコインを購入し、海外でUSDCに交換するルートが一般的です。送金手数料と為替差を考慮すると総コストは1%前後になり、国内直接購入に比べて割高になるケースもありますが、USDTなど一部のステーブルコインは国内取引所で取り扱われていないためこの方法でしか取得することができません。
ステーブルコインは儲かる?についてよくある質問
- ステーブルコインは運用しないと意味がない?
- どのステーブルコインが日本で買える?
- ステーブルコインはなぜ種類が多い?
疑問を解消してから投資判断を行うことで、リスクを抑制しやすくなります。
ステーブルコインは運用しないと意味がない?
ステーブルコインは、1枚1ドルで価格が固定されており、変動しても0.001ドル単位でしか上下しません。
購入してただ持っているだけの場合、レバレッジ無しのドル投資とほぼ同じ状態になります。
そのため、ステーブルコインはただ持っているだけではなく、レンディング等に預け入れて運用することがステーブルコインを利用した主な収益獲得方法となります。
仮想通貨は常に価格が動き続けるのが基本ですが、ステーブルコインはそのルールを無視して、仮想通貨にもかかわらず値段が一定で、安定した利率で儲けることができる存在なのです。
どのステーブルコインが日本で買える?
現在、国内仮想通貨取引所で日本円で直接購入できるステーブルコインは、USDC、DAIの2つです。
USDCはSBI VCで、DAIはほとんどの国内取引所で取り扱われています。
ステーブルコインには、もう1種「USDT」というトークンがあるのですが、こちらはまだ国内で上場しているところはありません。
それぞれのステーブルコインの詳細解説は以下の記事をお読みください。
ステーブルコインはなぜ種類が多い?
種類が多い主な理由は「発行者の所在地」「裏付資産の通貨」「ペッグ維持方式」が多様化しているためです。
ドル建てだけでもUSDC、USDT、DAI、FDUSD、BUIDL、PUSDなど多数あり、発行体が異なればリスク状況も変わります。
競争要因としては、送金先システムとの互換性や利回りキャンペーンが挙げられます。例えばDeFiで高利回りを得るために、特定チェーン対応のステーブルコインが用意されるケースがあります。
結果として、用途に応じて最適なステーブルコインを選択することが求められ、投資家は信用リスクと流動性を比較しながらポートフォリオを組む必要があります。
ステーブルコインの種類は以下の記事で解説しています。