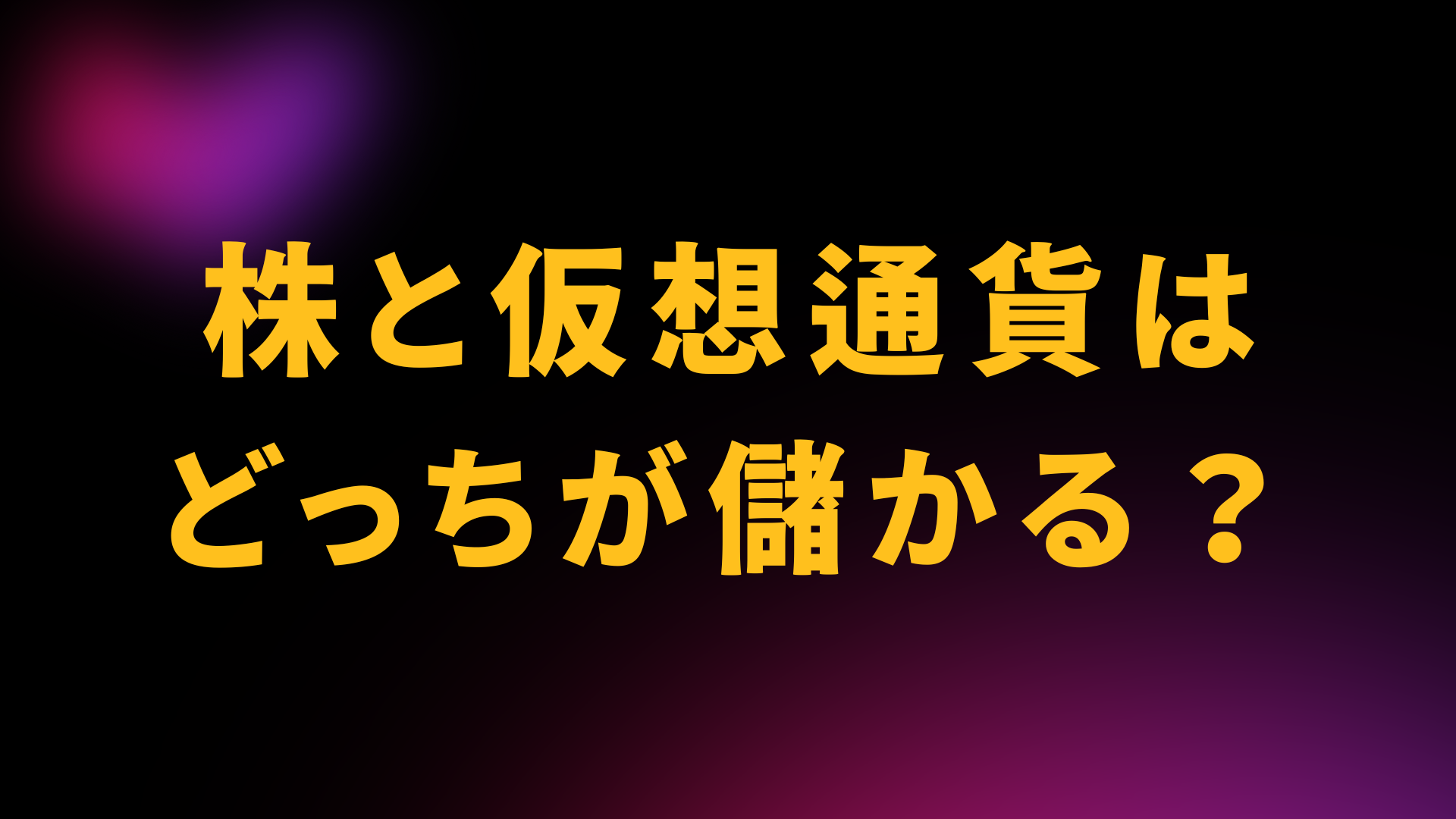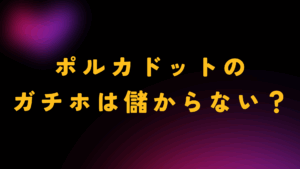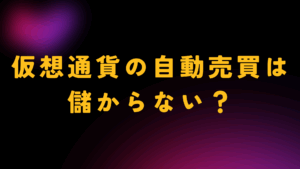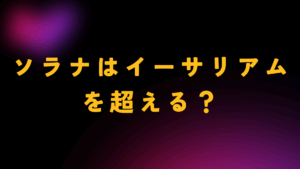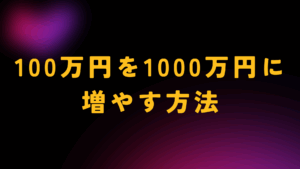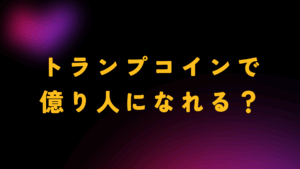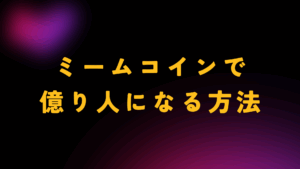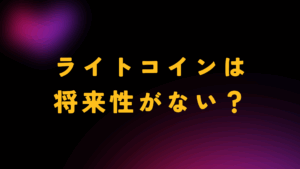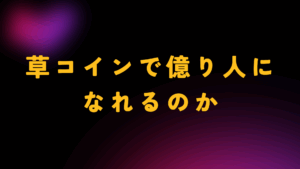本記事では、株と仮想通貨はどっちが儲かるのか、それぞれの収益性分析やメリット・デメリットの観点などから解説します。
両方に投資してみたいがどのように投資すればよいのかわからなくなっている方も、本記事で解説している投資方法を活用してみてください。
株と仮想通貨はどっちが儲かる?
株と仮想通貨はどっちが儲かるかですが、2024年だとビットコインが年間+113 %、S&P500が+25% と、仮想通貨が株式を大きく上回りました。
ただ、年間リターンだけで「どちらが儲かるか」と結論づけるのはおすすめしません。なぜなら、観測期間とリスク水準が違えば簡単に結論が変わるからです。
ビットコインの価格は大きく動きやすい点も考慮しなければいけません。
例えば、2024年の1年間の値動きを表す1年実現ボラティリティという指標を見ると「約50%」の変動がありました。一方で、株の代表的な指標であるS&P500は「約20%」と、ビットコインより安定しています。
投資の世界では「大きなリターンを狙うほど、大きなリスクもある」のが基本ルールです。
もしこの関係を無視して儲かった、儲け損ねただけを気にすると、実際に投資をしたときに、想像以上の値下がり(ピークからの下落)に耐えられなくなることがあります。
加えて、株式は配当や自社株買いという仕組みが存在し、株の価値を支える土台になります。
一方で仮想通貨は主に安く買って高く売る売買差益でリターンを得るのが主流ですが、最近はビットコインのレンディングやイーサリアムのステーキングなど、収益を得る方法が複数あるのが特徴です。
総合的に見ると、短期で爆発的リターンを狙うなら仮想通貨、長期での複利運用を重視するなら株式、そんな棲み分けが有効だと言えます。
仮想通貨の代表であるビットコインは、すでに価格が高いので遅いと言われますが、今からでも遅くありません。
その理由は以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
ビットコインは今からだと遅い?最新の相場状況から間に合うのか徹底解説
株式投資の収益性を分析
株式投資は、値上がり益に加えて配当という定期的な収入が得られる点が特徴です。
配当は会社がどれくらい利益を出しているかを反映しているので、もし配当が減った場合は「会社の調子が悪いかも」と早めに気づくヒントにもなります。
これによって投資家はリスクを調整しやすくなるのです。
2024年には、S&P500に入っている大企業たちが、配当や自社株買いを合わせて100兆円以上を株主に還元しました。
また、自社株買いには株の価値を高める仕組みがあります。
会社が市場から自分の株を買い戻すと、残っている1株あたりの利益(EPS)が増え、結果的に株価や株式指数の成績を押し上げる効果があるのです。
EPSとは、「Earnings Per Share」の略で「1株当たり純利益」です。
企業の収益性や成長性を評価する際に使われる重要な指標です。
リターンのデータを長期視点で見ると、配当は再投資した方が複利効果を高めることがわかってます。
実際、過去30年の米国株トータルリターンのうち約40%が配当再投資由来と試算されています。
また、リーマン・ショックのあと、世界的に金利がとても低い時期が続きました。
このとき株式は「シャープレシオ」という指標で見ても安定していました。
この数字が0.6〜0.8の間で安定していたことから、株式はリスクを考慮したうえでも他の投資対象より有利な立場を保っていた、ということが分かります。
もう一つ無視できないのが税制の安定性です。日本の上場株式は譲渡益・配当ともに20.315%の申告分離課税で完結し、損益通算と3年繰越控除も可能です。
税後リターンを見積もりやすいことは、長期シミュレーションを行う際の大きな安心材料になります。
仮想通貨投資の収益性を分析
ビットコインは2024年に+113 %と三桁成長を達成しましたが、この上昇は現物ETF承認と半減期期待という二大イベントに強く依存していました。
ビットコインの半減期とは?なぜ価格が上がるのか、どう投資すれば儲かるか解説
価格を押し上げる要素が明確な反面、その要素が消えた後はボラティリティが上昇する傾向があります。
実際、年初来リターンは+17%程度に収束し、短期的な値幅は増えつつあります。
しかし、収益を得る他の方法としてレンディングが注目されています。レンディングは、価格変動リスクをほぼ受けない状態で年利10%程度の利回り収入を得られます。
仮想通貨レンディングとは?メリットやリスク、どれだけ増えるのかを解説!
「リスクに見合ったリターン」を表すシャープレシオで見ると、ビットコインは株式より良い成績を出す時期もあります。
ですが、その結果は極端で、「運が良いときはすごく儲かるけど、悪いときは大きく損をする」という振れ幅の大きさが特徴です。
最近はETFを通じて大きな資金が流れ込み、市場は少しずつ安定してきています。それでも、リスクをあまり取れない投資家にとっては、精神的にハラハラしやすい投資対象であることに変わりはありません。
株式投資と仮想通貨投資のメリット・デメリット
株式投資と仮想通貨投資のメリット・デメリットを比較しました。
株式投資のメリット・デメリット
- 配当と自社株買いによるインカムが存在する
- 流動性や市場インフラの信頼性が高い
- 成熟市場ゆえの平均リターンの低下と情報優位性の獲得難易度が高い
配当と自社株買い によるインカムが存在し、長期複利を安定的に享受できます。配当再投資戦略は手堅い資産形成術として広く浸透しており、NISA の拡充策によって税優遇も強化されました。
米国株では主要銘柄の1日の取引額が数十億ドルにのぼるため、大きな資金を動かしても値段が大きくズレにくい(スリッページが少ない)という特徴があります。
さらに、市場が急に大きく下がったときに一時的に売買を止める「サーキットブレーカー」や、取引後の決済ルールが整っているので、安全面の仕組みも充実しています。
欠点としては、成熟している市場のため、平均リターンの低下と情報優位性の獲得難易度があります。
多くの投資家が情報を徹底的に分析しているため、「他の人より有利な情報を手に入れて勝つ」のが難しくなっているのです。
また、配当課税と再投資課税の「二重課税構造」により、手取りリターンが想定より低下する局面もあります。
仮想通貨投資のメリット・デメリット
- 高ボラティリティと24時間市場
- 規制の未熟さ
- 利益機会が多いが急落トリガーにもなり得る
仮想通貨投資の最大の強みは高ボラティリティと24時間市場が開いていることです。
取引機会が途切れず、短期トレーダーは値幅を取りやすい環境が整っています。
仮想通貨は1000倍の価格上昇を狙える銘柄もたびたび登場しており、リスクは高いですが一回で大きなリターンを稼げるのが特徴です。
仮想通貨で1000倍になった銘柄を紹介!今後狙い目な分野や見つけ方も解説
また、レンディングやイールドファーミングなど、株式市場には存在しない収益手段を活用できることも魅力です。
一方で規制の未成熟さは大きなリスク要因です。国境を越えた取引が容易な反面、税務申告の煩雑さやハッキング被害時の資産保護が未整備なケースが多数存在します。
日本では暗号資産の所得雑所得課税(最高55%)になるため、高所得者ほど手取り利回りが下がる点に注意が必要です。
仮想通貨市場には特有の欠点もあります。代表的なのが「レバレッジ取引」です。少ない元手で大きな取引ができる仕組みですが、これは利益のチャンスになる一方で、急な値下がりの引き金にもなります。
特に市場が大きく動いたとき、取引所の仕組みが追いつかず、一気に価格が崩れ落ちる「ロングスクイーズ」と呼ばれる現象がよく起こります。
これは、レバレッジ取引をしている投資家が一斉に強制的に売らされることで起きるもので、大きな損失を被る可能性が高い現象です。
株と仮想通貨の関係性
以前のビットコインと株式の相関係数は0.1〜0.2と低く、ビットコインは「デジタルゴールド」として分散投資効果が期待されていました。
しかし2024年に現物ETFを通じた資金流入が本格化すると、相関係数は0.3台後半まで上昇しており、ビットコインが分散化につながらなくなってきています。
ポートフォリオ全体のボラティリティを抑えつつ、リターン期待値を引き上げたい場合、全体の1〜5%程度の比率で仮想通貨を組み込むのがおすすめとされています。
以下の記事では、100万円を1000万円にする方法として株式投資と暗号資産投資それぞれの選択肢を解説しています。
100万円を1000万円にする方法6選!リスクを抑えて楽に増やす方法も解説!
株式と仮想通貨は何で価格変動するのか
株式と仮想通貨はマクロの経済状況で価格変動しやすい資産です。
主に政策金利、財政政策、GDP成長率などの変化に敏感です。
また、仮想通貨は新しい規制のニュースが価格変動に影響します。
株式市場では類似の規制ショックは相対的に少なく、経済状況で説明できる部分が大きいため仮想通貨より予測しやすいでしょう。
株と仮想通貨はどのように分けて投資すればいい?
資産配分を考えるときに大事なのは、「株」と「仮想通貨」が同じタイミングで動くわけではない、という点です。
景気が良くなり企業の利益が増えるときは、株式の方が有利になりやすいです。一方で、中央銀行が金融緩和をしてお金の量が増えると、その余ったお金が仮想通貨に流れ込み、株より仮想通貨の方が大きく上がることもあります。
このようにリスクの種類が違う資産を組み合わせて持つことで、どちらかが調子を崩しても、もう一方がカバーしてくれる可能性があります。
もうひとつ重要なのが時間分散とリバランスです。株式は配当再投資を軸にしたバイ・アンド・ホールドでも複利が効きますが、仮想通貨は下落幅が大きいので「いつ買うか」がリターンを左右します。
そこで、仮想通貨については定額積立(ドルコスト平均法)を用いて取得単価を平準化し、含み益が想定比率を超えたら株式側へ移す「定率リバランス」を機械的に行う方法が合理的です。
ただ、ビットコインの積立投資はやめとけと言われることも多いです。以下の記事では、その理由や対策しながら稼ぐ方法などを解説しています。
ビットコインの積立投資はやめとけ?理由や失敗を招く罠などを解説
最後にリスク管理の指針を整理しましょう。
- 許容損失額をポートフォリオの〇%と数値化する
- 仮想通貨レバレッジは原資の1倍以下(現物中心)に抑える
- ストップ注文とアラート設定で夜間の急変に備える
この3ステップを最低限対策をしておくのがおすすめです。
仮想通貨と株はどっちが儲かる?についてよくある質問
- 仮想通貨はやめとけと言われる理由は?
- 短期なら仮想通貨の方が有利?
- 配当とステーキング報酬はどちらが得か?
- 株式と仮想通貨を組み合わせた場合のヘッジ効果は?
仮想通貨はやめとけと言われる理由は?
「仮想通貨はやめとけ」という助言には以下の要因があります。
- 税制が不利
- 規制がグレー
- 流動性と市場構造に脆弱性がある
まず税制です。日本では暗号資産の所得が雑所得扱いとなり、最高 55 % の累進課税が適用される可能性があります。株式の申告分離課税 20.315 % と比較すると、税後リターンが大幅に削られる現実は無視できません。
そして規制のグレーゾーンが挙げられます。2024 年の米国現物ETF承認やEUのMiCA規則で一定の枠組みが整いつつあるとはいえ、トークンごとの法的位置づけは国によって千差万別です。
ビットコインはやめた方がいい?リスクやまだ間に合うのかを解説!
短期なら仮想通貨の方が有利?
短期売買だけを比較すると、仮想通貨はボラティリティが高い分だけ値幅取りのチャンスが多く、有利に見えます。
実際、24時間取引と高レバレッジを武器に、日次で5% 以上の振れ幅を狙うデイトレーダーも存在します。しかし、ボラティリティが高いということは損失幅も大きいという裏返しです。
強制ロスカットが一瞬で実行される無期限先物を利用する場合、リスク管理を怠れば数分で資産が半減するリスクも現実的です。
そのため「短期=仮想通貨が必ず有利」とは言い切れません。
短期取引で儲ける手段の1つには、FXもあります。以下の記事では、仮想通貨とFXではどっちを選んだ方が稼げるのか解説しています。
仮想通貨とFXはどっちが儲かるのか徹底比較!投資家タイプ別診断も紹介
配当とレンディング報酬はどちらが得か?
配当は企業の利益を原資とするため、減配・無配が起きにくい成熟企業では年率2〜4 %程度の安定収入になります。
配当再投資による複利効果は過去50年のデータで一貫して正のリターンを示し、「もらって再投資すれば右肩上がり」という再現性の高さが魅力です。
レンディングは、仮想通貨をレンディング業者に一定期間預けることで、利回り報酬がもらえます。
レンディングはステーキングと比較して、価格変動がほぼないステーブルコインが預けられるため、ステーキングよりリスクを抑えて同程度の利回りを享受できます。
仮想通貨レンディングの詳細ややり方は以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
仮想通貨レンディングとは?メリットやリスク、どれだけ増えるのかを解説!
株式と仮想通貨を組み合わせた場合は分散効果はある?
2020〜2021年のデータでは、株式とビットコインを9:1の割合で持つことで、リターンを1.3倍に引き上げながらポートフォリオの安定性を微増させたという研究があります。
ただ、近年は株式と仮想通貨の相関性が高く、両方に投資しても分散投資になりにくいのが現状です。
そのため、分散投資目的で両方に投資するのはあまり効果的ではないでしょう。
株と仮想通貨はどっちが儲かる?-まとめ
株と仮想通貨はどっちが儲かるのかを、本記事で分析しました。
- 短期で高い値幅を狙うなら、24 時間取引と高ボラティリティを武器にする仮想通貨が有利に映る。
ただしレバレッジ管理を誤れば一夜で資産が溶けるリスクも背負います。 - 長期で複利と安定キャッシュフローを重視するなら、配当再投資と税制の読みやすさを備えた株式が王道。
ただし景気循環に伴うバリュエーション調整は避けられません。
最適解はあなたの許容損失額・投資期間・税務環境・情報処理能力によって変わります。
まずは生活防衛資金を除いた「リスク許容度の 5 〜 20 %」を上限に仮想通貨を試験導入し、残りを国際分散株式で保有する、そんなステップアップ方式が、初心者にも経験者にも共通する現実的な出発点となるでしょう。