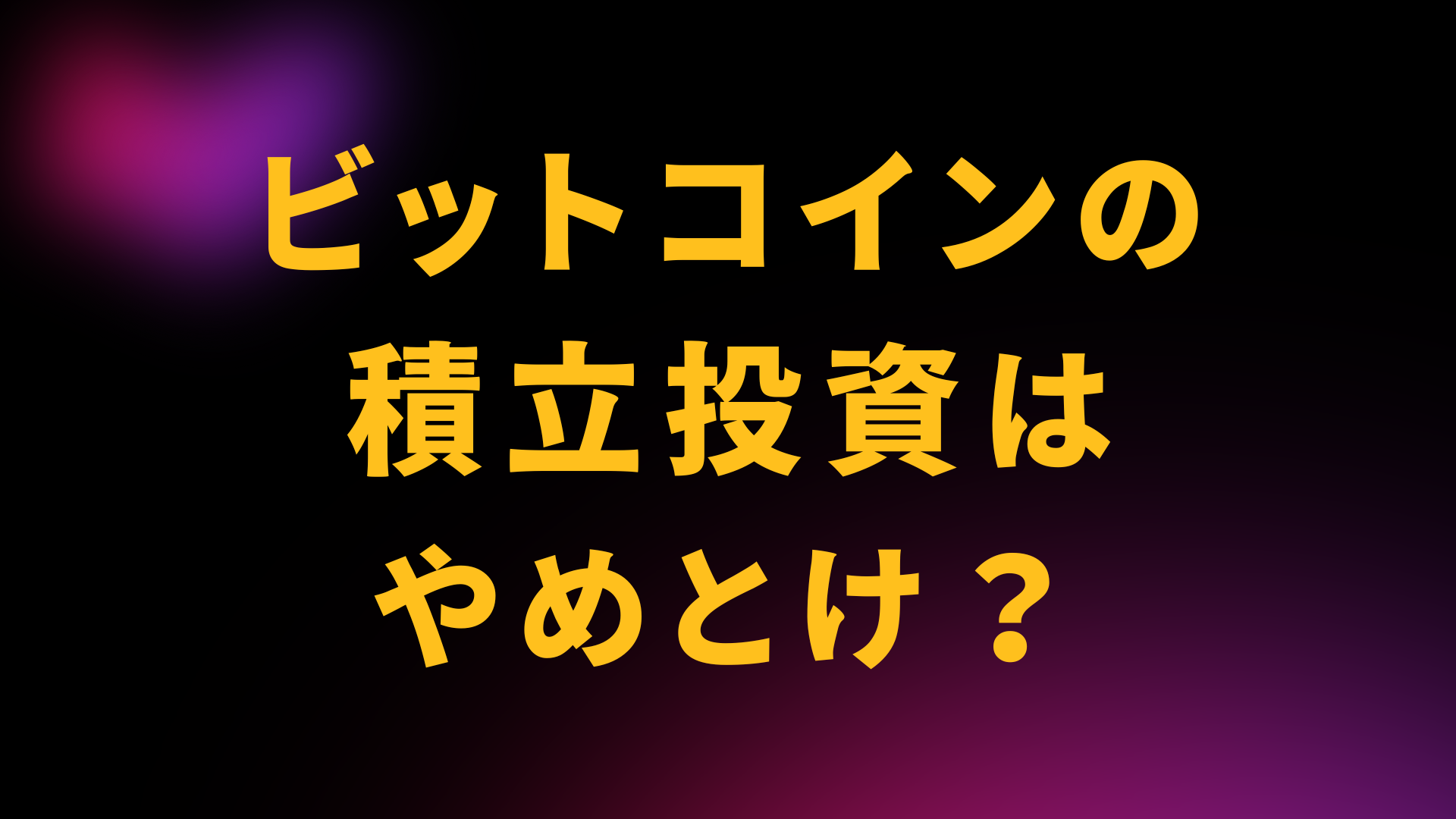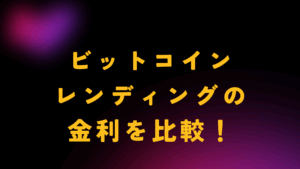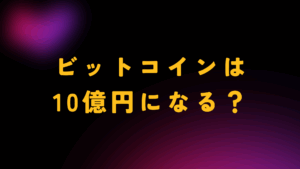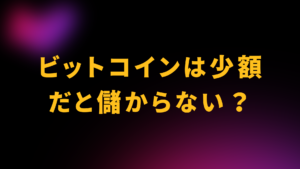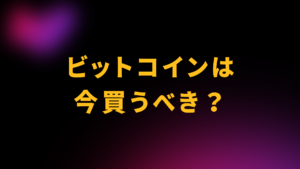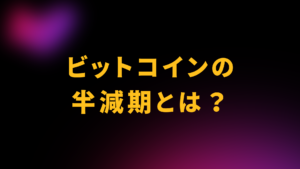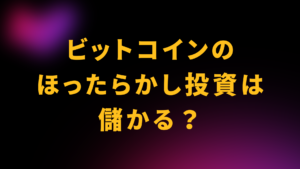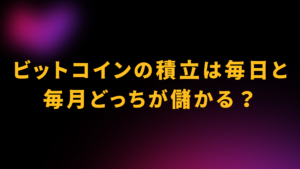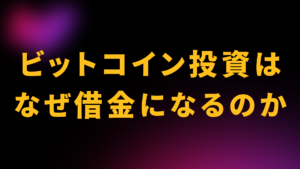ビットコインの積立投資で大きな利益を出している人がいますが、80%を超える暴落に心をへし折られた投資家がいるのも事実です。
本記事では、ビットコインの積立投資は行うメリットがあるのか、どれくらいのリスクがあるのかなどを解説し、積立投資をやめるべきか解説します。
ビットコインの積立投資はやめとけって本当?
ビットコインの積立投資はやめとけと言われますが、それは以下のような理由があるからです。
- 高リターンだが極端なドローダウンを伴う二面性
- 長期保有でプラスでも途中の急落・取引所リスクが大きい
- 過大比率や高頻度積立がリスク調整後リターンを悪化させる可能性
ビットコインはやめた方がいい?リスクやまだ間に合うのかを解説!
高リターンだが極端な損失リスクを伴う可能性がある
ビットコインは発行上限が2,100万枚と決められた希少性の高いデジタル資産ですが、過去15年で年平均120%という驚異的な上昇率を記録してきました。
ところが、同じ期間には‐84%や‐76%にも達する暴落も何度も経験しています。
ドローダウンとは「過去の最高値からどれだけ価格が下落したか」を示す指標で、これが深いほど投資家の心理的負担は大きくなります。
この“高リターンと深いドローダウンの共存”こそが、積立投資を「やめとけ」と警告する最大の理由です。上昇局面では一括投資より積立の方が平均取得単価を押し下げる効果が期待できますが、暴落局面に入ると含み損が長期化しやすく、計画を途中で断念するリスクが高まります。
さらに、ビットコイン市場は24時間365日休まず動き、株式や債券よりも桁違いに高いボラティリティ(価格変動幅)を示すため、感情的な売買を誘発しやすい点も“やめとけ論”を後押ししています。
ビットコイン投資がなぜ借金になるのか、借金にならずに安全に投資する方法は以下の記事で解説しています。
ビットコイン投資はなぜ借金になるのか?借金になるやり方や事例を解説
長期保有でプラスでも途中の急落・取引所リスクが大きい
シミュレーションによれば、毎月1万円ずつ積み立てて10年保有した場合、元本割れで終わる確率は1%未満に低下します。
それでも「途中で‐40%を超える評価損」を経験する可能性は高く、精神的な苦痛は避けられません。長い時間軸で最終的に報われるとしても、途中の“谷”が深すぎると続けるのが難しいのです。
加えて、取引所そのものの破綻やハッキングという“非価格リスク”も軽視できません。
過去にはMT.GOXやFTXといった大手の破綻で、積立中の資産が引き出せなくなった事例がありました。長期的にプラスが期待できても、取引所のガバナンスが崩れれば投資成果は一瞬で無に帰します。
このため、ビットコイン積立は「価格暴落リスク」だけでなく「カストディ(保管)リスク」を二重に負っている点が、他資産の積立と根本的に違うといえます。
積立投資し過ぎると逆にリスクが高くなりリターンが減る
積立割合をポートフォリオの大半にまで広げたり、毎日など高頻度で購入したりすると、リスクに見合ったリターンが得られにくくなります。
毎日積立は価格ブレを細かく吸収できる半面、取引手数料とスプレッドがかさみやすく、長期では利益率中央値が約3ポイント低下しました。
また、資産全体の5割以上をビットコインに振り向けると、一回の暴落で家計全体が損失を被る可能性が高まります。
リスク調整後リターン(シャープレシオなど)を最大化したいなら、暗号資産の割合は総資産の数%〜多くても20%程度にとどめるのが一般的な“安全域”とされています。
要するに、積立効果を得たいなら「買い過ぎず・頻度を上げ過ぎず・手数料を抑える」三点を同時に満たさなければなりません。
ビットコインの積立は毎日と毎月のどっちが得なのか徹底比較
ビットコインの積立投資は毎日と毎月、どっちの方が得をするのか、徹底比較します。
そもそもビットコイン投資が今からだと遅いのかが気になる人は、以下の記事をお読みください。
ビットコインは今からだと遅い?最新の相場状況から間に合うのか徹底解説
毎日積立は購入価格が均一になりドローダウン緩和に有効
日次積立は1日ごとの価格ブレを細かく拾うため、平均取得単価がより平準化されます。2018年末の急落局面を例に取ると、月次積立より日次積立の方がドローダウンを約10%浅く抑えたパターンが確認されました。
価格が荒れる相場で「とにかく下値を厚く拾いたい」場合、日次の細分化は心理的な安心感をもたらします。ただし、このメリットは手数料とスプレッドで相殺されるリスクがある点を忘れてはいけません。
日次を選ぶのであれば、取引所の明示手数料とスプレッドをできる限り低く抑え、実効コストを月次と同等水準に近づける工夫が不可欠です。
毎月積立はコスト2〜3割減で純利益率が優勢
月次積立は取引回数が少ない分だけ明示手数料もスプレッドコストも抑えやすく、実効コストは日次より2〜3割低減することが一般的です。
価格変動リスクを多く負う代わりに、長期の手取りリターンでは優位に立つ傾向があります。
急落リスクを強く意識する投資家は日次、コスト効率を重視する投資家は月次、と目的で使い分けるのが現実的な選択です。「どちらが絶対得か」ではなく、自身のリスク許容度と投資期間に合った頻度を選ぶことが肝心です。
なお、週次や隔週など中間的な頻度を採用して、両者のデメリットを緩和する手法も検討する価値があります。
ビットコインの積立投資を毎日と毎月どっちを選択すれば良いか、さらに詳しく解説した記事もあるので、お読みください。
ビットコインの積立投資は毎日と毎月どっちが儲かる?どっちを選べばよいか解説
ビットコインの積立はどこがいい?取引所と手数料を見極める
ビットコインの積立投資はどこで行うのがおすすめなのか解説します。
主要取引所の積立手数料は年率0.5〜1.5%で1番おすすめ
国内外の大手取引所が提供する自動積立プランでは、積立専用手数料やスプレッドを合わせた実効負担が年率換算0.5〜1.5%の範囲に収まっています。
海外大手が0.7%前後、国内大手が1%前後とやや割高なのが現状です。
数字だけ見ると小さく感じますが、10年で単利計算しても5〜15%のコストがかかる計算になるため、軽視はできません。特に少額積立ほど手数料比率の影響が大きくなります。
取引所を選ぶ際は「長期で積み立てるほど手数料が重石になる」ことを念頭に置き、サービス比較を行いましょう。
明示手数料・スプレッド・最小発注単位を比較する
取引所を比較する際は以下の点を抑えて比較しましょう。
- 明示手数料
- スプレッド
- 最小発注単位
手数料が0%でもスプレッドが0.5%あれば実質コストは高くつきますし、最小発注単位が大きいと“端数”を残しやすく、積立効率が低下します。
また、海外取引所では最低手数料が0.0005BTCなど固定額で設定されているケースがあり、少額積立では手数料率が跳ね上がることもあります。
事前に「自分が想定する最小注文額」を基準にコストシミュレーションを行うと、計画が狂いにくくなります。
最後に、証拠金比率や監査報告の公開頻度などガバナンス面も含めて比較し、破綻リスクに備える姿勢が重要です。
ビットコインの積立投資をシミュレーション
ビットコインの積立投資のシミュレーション結果は、すでにさまざまな報告があります。
たとえば大手取引所のCoinbaseの公開データで、2017 年 12 月 18 日(当時の史上最高値付近)から週 100 ドルずつ 2021 年 1 月 25 日まで積み立てたケースがあります。
この検証結果では、総投資額 16,300 ドルが約 65,000 ドルに膨らみ、約 299 % のリターンとなった。暴落直後も買い続けるため平均取得単価が下がり、長期上昇局面の利益が増えたと言えます。
arxivの学術調査によれば、ビットコインは週次・月次スケールでは短期的な激しいゆがみが平均化されやすいという結果も出ています。
すなわちビットコインのドルコスト平均法は「高ボラティリティ資産の荒波を時間で平滑化する」メカニズムとして機能しやすいのです。
ビットコインの積立投資のメリット
- 定額購入で取得単価を平準化できる
- 自動化して感情的な取引を回避できる
- 少額から始められる
- 法定通貨建て資産を減らして分散投資できる
- 供給上限と半減期が価格下落を抑える
定額購入で取得単価を平準化できる
ドルコスト平均法は「価格が安いときは多く、高いときは少なく買うことで平均購入単価をならす」手法です。
ビットコインのように価格変動が大きい資産では、この効果が特に大きく、長期で見ると一括投資よりボラティリティ調整後リターンが安定する傾向が確認されています。
ドルコスト平均法のような定額購入を徹底すれば、短期的に含み損が出ても長期的に平均取得単価が下がりやすく、最終的な収益のブレを抑えられます。
ただし、トレンドが非常に強い上昇局面では一括投資が優位に立つパターンもあり、積立はあくまで“平均を狙う戦略”である点を理解しておく必要があります。
自動化で感情的な取引を回避できる
取引所の自動積立サービスを利用すれば、チャートを眺め続ける時間と精神的ストレスを大幅に減らせます。
価格が24時間動く暗号資産市場では、睡眠中の急落や急騰に心理が振り回されがちですが、自動化により“見守るだけ”で済むことが大きなメリットです。
また、定期的な発注・出庫を自動化することで、ヒューマンエラーや手続き忘れによる機会損失を防げます。
Coincheckのような国内取引所は自動積立投資サービスを提供しており、便利に投資できます。ただ、自動積立は取引所ではなく販売所での購入になるので、スプレッドは高くつきます。
少額から始められる
国内主要取引所の積立は1回あたり1,000円程度から設定可能で、投資経験の浅い層でも心理的ハードルが低いのが特徴です
少額で始めて、値動きに慣れながら徐々に比率を高める“スモールステップ学習”は、ビットコイン市場の激しい変動に順応する現実的な方法です。
実際に自分の資金が動くことで得られる学習効果は、机上の勉強より理解を深めるうえで有用です。
さらに、少額投資であれば最悪ゼロになっても生活に支障が出にくく、リスク許容度の範囲内で試行錯誤しやすい点も魅力と言えるでしょう。
法定通貨建て資産を減らして分散投資できる
ビットコインは株式や債券と異なる需給要因で価格が動くため、長期ポートフォリオに組み入れると全体のリスクを抑えつつ期待リターンを押し上げる“分散効果”が得られます。
伝統的資産の値動きが停滞する局面でも、ビットコインが独自の材料で上昇する可能性があることから、積立を通じて「時間分散」と「資産分散」を同時に実現できる利点は大きいです。
ただし相関が低いからといって逆相関ではない点に注意し、過大比率にはくれぐれも気を配りましょう。
供給上限と半減期が価格下落を抑える
ビットコインは4年に一度、マイニング報酬が半減する“半減期”を迎え、最終的な発行枚数は2,100万枚で頭打ちになります。
このルールがコードに組み込まれているため、株式の増資や法定通貨の量的緩和のような“希薄化”が構造的に起こりにくい点が魅力です。
供給量が予見可能であることは「長期ホルダーが将来のインフレに怯えにくい」という安心感につながります。結果として、積立投資家にとっては“買った後のルール変更リスク”が小さいことが信頼性に直結します。
ただし、価格が将来必ず上がる保証ではなく、需要が伸び悩めば価格停滞や下落も十分あり得るため、供給上限を過信しすぎないバランス感覚が必要です。
ビットコインの半減期とは?なぜ価格が上がるのか、どう投資すれば儲かるか解説
ビットコインの積立投資のデメリット
- 短期で70%超の下落リスクがある
- 取引所破綻・ハッキングによる資産喪失リスクがある
- 他資産への機会費用が発生する
短期で70%超の下落リスクがある
ビットコインは2021年11月の最高値から2022年11月までにほぼ-76%下落しました。これは株式市場でいえば一次大恐慌級の値動きに相当します。
しかも暗号資産市場はレバレッジ取引が盛んなため、下落スピードが極端に速く、含み損がみるみる—数日で—膨らむケースが珍しくありません。
短期急落の厄介な点は、積立額そのものは小さいのに評価額のマイナスが心理的許容範囲を大きく超えやすいことです。
たとえば月1万円の積立でも、直近までの含み益が“砂時計をひっくり返すように”一瞬で消えると、計画を継続するモチベーションが一気に冷えこみます。
さらに、ドローダウンが深いほど回復に必要な上昇率は指数関数的に増えます。
70%の下落を帳消しにするには、元値から約233%の上昇が要る計算です。これは“いつか戻る”という楽観を裏切る現実であり、長期視点でも無視できない負荷となります。
取引所破綻・ハッキングによる資産喪失リスク
取引所破綻リスクはカストディリスク(資産保管リスク)の一種で、価格変動とは別軸の脅威です。
2014年のMT.GOX事件、2022年のFTX破綻では、預け入れたビットコインがほぼ回収不能になりました。暗号資産はブロックチェーン上では盗難を防げても、取引所内部での不正アクセスや資金流用までは防げないためです。
国内の登録業者は金融庁の規制により分別管理を義務づけられていますが、経営破綻時にどこまで顧客資産が守られるかは“契約の文言と裁判所の判断”に委ねられます。
積立は資産を長期にわたり預ける運用なので、取引所のガバナンス体制、第三者監査報告の有無、損害保険の加入状況を必ず確認しましょう。
リスク低減策としては「月次で買い付け→即ハードウェアウォレットへ出庫」が鉄板です。出庫手数料は1回数百円〜数千円かかりますが、大暴落や経営破綻で資産が蒸発するより遥かに安い保険料と考えられます。
他資産への機会費用が発生する
ビットコインに資金を固定すると、その分だけ株式や不動産など成長資産への投資余地が狭まります。
例えば、2023年の米国株はAIブームで約25%上昇しましたが、同期間のビットコインが横ばいだった場合、資金配分を誤ると機会損失が浮き彫りになります。
機会費用とは「ある選択をしたことで得られなくなる潜在的利益」のことです。ポートフォリオの多様化が不十分だと、暗号資産の停滞期に資産全体の成長が頭打ちになるリスクが高まります。
解決策は、ビットコイン積立比率に上限を設け、定期的なリバランスで株式・債券・現金ポジションを回復させることです。こうすることで、暗号資産市場の停滞が家計全体に与える影響を和らげられます。
ビットコインの積立投資が向いている人
- 10年以上の長期運用を視野に入れられる
- 高いリスク許容度で急落にも動じない
- 定期的な可処分所得で自動積立と家計管理を両立できる
- 分散投資を重視しポートフォリオの一部に留められる
10年以上の長期運用を視野に入れられる
ビットコインのシミュレーションによると、10年以上の積立では元本割れ確率が1%未満と大幅に低下します。したがって、投資期間を“二桁年”で設定できる人は積立投資と相性が良く、時間分散と複利効果を十分に享受できます。
長期視点を取るには、学費や住宅頭金など近い将来に必要な資金を分離し、生活防衛資金を確保しておくことが前提条件です。
資金拘束が精神的ストレスに変わらないよう、ライフイベントとの資金計画を重ね合わせて検討しましょう。
長期運用を覚悟すると、「途中で暴落があっても止めない」というマインドセットが身につきやすく、計画逸脱のリスクを抑えられます。
高いリスク許容度で急落にも動じない
ビットコインはボラティリティが株式の約3倍で、‐50%超の下落が数カ月以内に起こることも珍しくありません。
これに耐えられるリスク許容度とは「大幅な含み損でも生活やメンタルが破綻しない度合い」を指します。
「保有資産の時価が半分になっても家計が回るか」を試算してみることが第一歩です。試算結果を見て「まだ眠れる」と感じるか「胃が痛い」と感じるかで、自分が積立向きかどうかを判断できます。
リスク許容度が高い人ほど、市場急落時に冷静さを保てるため、ドルコスト平均法の“安値拾い”メリットを最大化できます。
定期的な可処分所得で自動積立と家計管理を両立できる
毎月の給与や事業収入から余裕資金を生み出せる人は、自動積立の強みをフルに活用できます。
積立額を給与振込口座からの自動引き落としに設定すれば、手間なく継続できるうえ、家計の固定費感覚で管理できるからです。
積立額の目安は、可処分所得の5〜10%以内が一般的です。生活費を圧迫しない水準から始め、収入増や生活コストの変化に応じて調整すると、無理のない範囲で長期計画を守れます。
可処分所得が安定している人ほど積立中断リスクが低く、長期運用で統計上のプラスリターンを得やすくなります。
分散投資を重視しポートフォリオの一部に留められる
暗号資産をポートフォリオの20%以内に抑え、残りを株式・債券・現金で構成する投資家は、ビットコインの高ボラティリティを相殺しやすい傾向があります。
相関が低い資産に幅広く投じることで、全体リスクをコントロールできるからです。
分散投資を重視する人は、資産配分が崩れた際に“定期リバランス”でビットコイン比率を戻す習慣も持っています。これが結果的に「高値で売り、安値で買う」メカニズムとなり、リスクリターン効率を高めます。
積立額を決める際には、ポートフォリオ全体で目標リスクを設定し、その枠内で暗号資産比率を逆算すると失敗しにくくなります。
ビットコインの積立投資が向いていない人
- 短期値上がり益を狙うトレーダー
- 生活防衛資金が不足している人
- 価格変動に強い不安を覚える人
- 税務申告の煩雑さを回避したい個人
短期値上がり益を狙うトレーダー
積立は平均取得単価を平準化する“長距離走”向けの戦術です。短期売買で値幅を抜くトレーダーにとっては、定額購入は機会損失の温床になります。
価格が急騰する局面では一括投資やレバレッジ取引の方が圧倒的にリターンが高く、積立は相対的に見劣りします。トレード志向の人は、積立の“鈍さ”にストレスを感じ、途中解約する確率が高いです。
トレーダーとして成果を上げたいなら、短期指標とチャート分析に集中し、積立とは別枠で資金管理すべきでしょう。
生活防衛資金が不足している個人
ビットコインは24時間で二桁%動くことがあり、緊急時に現金化すると損失を固定する恐れがあります。生活防衛資金が足りないまま積立を始めると、急な出費で“売らざるを得ない”状況に追い込まれがちです。
最低でも3〜6カ月分の生活費を普通預金で確保したうえで、余剰資金を投資に回すのがセオリーです。防衛資金が枯渇したままの積立は、リスク管理というより危険な賭けに近くなります。
家計に余裕がない状態で積立を続けると、相場急落と家計急迫が同時に来る“ダブルパンチ”に耐えられず、結果的に損失を抱えて撤退するリスクが高くなります。
価格変動に強い不安を覚える人
含み損を抱えた瞬間に眠れなくなるタイプは、ビットコイン積立と相性が悪いです。リスク許容度が低いと、プロスペクト理論が示すように、痛みへの感度が利益への喜びの2倍以上になるとされます。
チャートを一日に何度も確認してしまう人は、価格が乱高下するビットコインではストレスが膨大になりがちです。結局、下落局面で積立を止めて安値売り、上昇局面で高値追いと、典型的な“損小利小”パターンに陥ります。
価格変動が怖い人は、ボラティリティが低い債券やインデックス投信から投資を始め、リスク慣れしてから暗号資産に挑戦する方が現実的です。
税務申告の煩雑さを回避したい個人
暗号資産の損益計算は“平均法”や“移動平均法”など計算方式が複雑で、年間取引が多いほど事務負担が増えます。
税金対応を最小に抑えたいなら、売却回数が少なく済む一括投資または伝統的資産中心の運用の方が向いています。
積立でリバランスや定期売却を頻繁に行うと、取引履歴をCSVでダウンロードして会計ソフトに取り込むなど、事務作業が膨大になります。
税理士に依頼すればコストがかさみ、セルフで行えば時間が奪われる二律背反です。
「投資はシンプルに済ませたい」という人は、暗号資産積立よりも少数銘柄の長期保有やロボアドバイザーを検討した方がストレスは小さいでしょう。
仮想通貨の積立投資はそもそも意味ない?
仮想通貨の積立投資は意味がないと言われることがありますが、それは以下の理由があります。
- ボラティリティや手数料が収益を相殺することがある
- 積立を途中で投げ出して負けてしまう
- 他資産との比較で期待リターンが見劣りする状況
ボラティリティや手数料が収益を相殺することがある
「積立は意味がない」という主張の多くは、ボラティリティ由来の含み損と手数料負担がリターンを食い潰すという論点に集中します。
事実、日次積立で手数料がかさんだ場合、シミュレーションでは利益率中央値が3ポイント下がりました。
しかし、その“手数料によるマイナス”はコスト管理でかなり削減できます。取引所形式+月次積立で実効コストを半減すれば、長期リターンがプラスになる確率は依然として高いままです。
結局のところ“意味がない”のではなく“コストを無視すると意味が薄れる”というのがデータの語る真相です。
積立を途中で投げ出して負けてしまう
積立が機能する前提は「途中でやめない」ことです。リスク許容度が低い投資家がビットコインに積み立てれば、暴落時に売却して平均取得単価を上げ、負けパターンを踏む可能性が高いです。
逆に高リスク許容度の投資家が株式だけに集中し、暗号資産を完全に排除するのも、ポートフォリオ最適化の観点では機会損失を拡大します。
積立の“意味”は投資商品の優劣ではなく、自分の性格・目的・時間軸に合うかどうかで決まると言い換えられます。
他資産との比較で期待リターンが見劣りするときがある
ビットコインは超高成長を遂げた一方で、2022年の弱気相場では世界株式にアンダーパフォームしました。株式が年率10%上昇する局面でビットコインが横ばいなら、積立リソースを株式に振り向けた方が合理的です。
したがって「今後10年でビットコインが株式より伸びる」と確信できない限り、全資金を暗号資産に投じるのはリスキーです。
分散投資を徹底し、各資産の期待リターンに応じて積立比率を調整することが、“意味ない”を“意味ある”へ変換する鍵になります。
ビットコインが停滞期に入っても、定期リバランスで他資産への配分を増やし、相対的に期待値を維持する仕組み作りが必要です。
ビットコインの積立投資はやめとけって本当?-まとめ
結論として、ビットコイン積立は「やめるべき投資」ではなく「条件付きで取り入れる投資」です。
10年以上の長期視点と高いリスク許容度を持ち、コスト・税金・セキュリティを総合的に管理できる投資家には分散効果と成長余地を提供します。
一方で短期志向や低リスク派、税務・技術対応に不安がある人には不向きです。自分の目標・資金・性格に照らし、メリットとデメリットを天秤にかけたうえで「続けるか、やめるか」の最終判断を下すことこそ、最も合理的な選択肢と言えるでしょう。