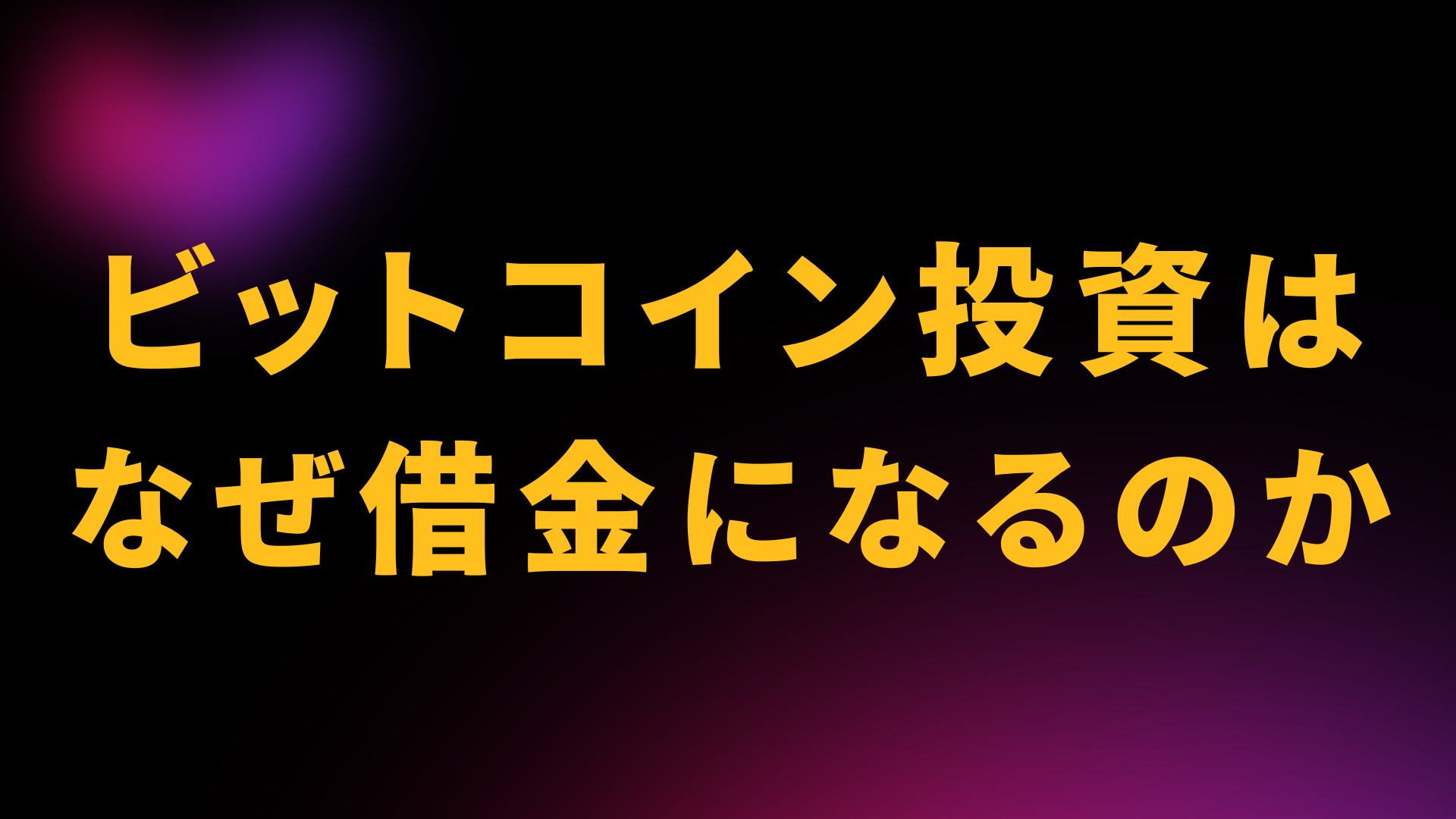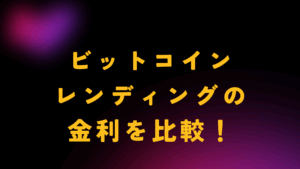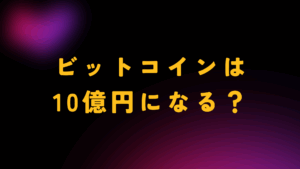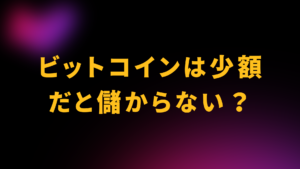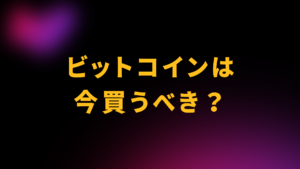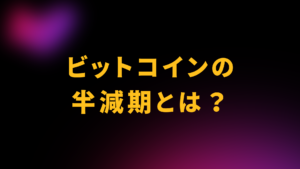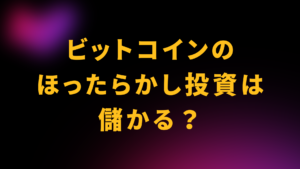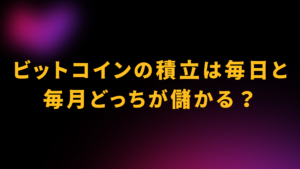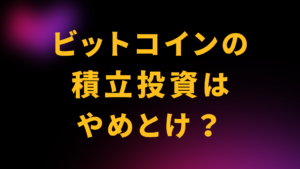ビットコイン投資は短期間で大きな利益を得る人がいますが、反対に多額の借金を負ってしまう人もいます。
本記事では、なぜビットコイン投資で借金をしてしまうのか、原因や借金をしないための対策方法を解説します。
リスクを低くしながらビットコインのリターンを狙いたい人は読んでおきましょう。
なぜビットコイン投資で借金を負うのか?
なぜビットコイン投資で借金を負うのか、主な理由は以下2つがあるでしょう。
- 値上がり益への期待とFOMO(取り残される恐怖)
- レバレッジ取引という「小さな元手で大きな賭け」できる手法
米調査会社 LendingTree が 2024 年に行ったアンケートによれば、暗号資産投資家の約 19%が「実際に借金をしてビットコインを購入した」と回答しました。
出典:Lendingtree
若年層ほど割合が高く、30 歳未満では 25%を超えるというデータもあります。ローン利用の敷居が下がった低金利環境と相まって、「借りてでも買え」という同調圧力が生まれやすい土壌が整ってしまったのです。
こうした風潮が増えてしまうと、ビットコイン投資はやめたほうがいいという人がより増えてしまうでしょう。
ビットコインはやめた方がいい?リスクやまだ間に合うのかを解説!
値上がり益への期待とFOMO(取り残される恐怖)
まず最も大きい動機は、過去の爆発的な値上がりによる成功例です。
ビットコインは 2017 年、2021 年、そして 2024 年と、数か月で 5 倍や 10 倍といった暴騰を経験しました。チャートを見れば、「次の波に乗り遅れたくない」という FOMO(Fear Of Missing Out)取り残される恐怖が自然と芽生えます。
この心理は、SNS や YouTube で可視化された「○○万円が1年で △ 億円になった」といった成功談が後押しし、合理的な計算を麻痺させます。
多くの人は「次も同じくらい上がるかもしれない」と期待を抱きますが、実際にはボラティリティ(価格変動の大きさを統計的に示す指標)が高い資産ほど、短期での下落リスクも同じくらい大きいことが見落とされがちです。
加えて、ビットコインは供給量が 2100 万枚に制限されているため、「有限だから将来必ず値上がりする」というストーリーが語られます。
確かに希少性は魅力ですが、短期的な価格は需要とレバレッジ残高に大きく左右されます。FOMO に突き動かされ借金まで背負ってしまう行動は、この“価格は永遠に上がり続ける”という誤解と表裏一体なのです。
ビットコインは今からだと遅いのか気になる人は以下の記事をお読みください。
ビットコインは今からだと遅い?最新の相場状況から間に合うのか徹底解説
レバレッジ取引という「小さな元手で大きな賭け」
レバレッジ取引とは、証拠金を担保に取引所から資金を借りて建玉を拡大する仕組みです。
株式市場では 2~3 倍が上限ですが、暗号資産取引所では 50 倍、100 倍、時に 200 倍もの倍率が一般向けに開放されています。「1% 動けば 100% の利益」という派手な広告は、少額資金の投資家にとって眩しい魅力です。
しかし倍率が高いほど、価格がわずかに逆行しただけで損失も同じ倍率で膨らみます。
証拠金維持率が一定ラインを割り込むと、取引所は強制的にポジションを清算(ロスカット)します。ロスカット時にマイナスが出れば、追加で差し入れる追証(追加証拠金)が必要になり、ここで初めて「借金」という現実が顕在化します。
問題は、多くの個人投資家が「ストップロス(指定した価格に到達したらすぐ決済する注文)を置いているから大丈夫」と自信を持っていても、板が薄い時間帯や急落時には注文が間に合わず、思った価格で決済されない点です。
結果として、想定より大きな損失が確定し、負債だけが残るケースが頻発します。
「小さな元手で大きな賭け」は、裏を返せば「小さなズレで致命傷」でもあるのです。
高倍率レバレッジが招くビットコイン借金地獄の実態
ビットコイン相場が活況を呈すると、取引所のレバレッジ残高は雪だるま式に膨らみます。
表向きは「たった数万円で巨大なポジションを握れる夢の仕組み」ですが、裏ではわずかな値下がりが連鎖的に清算を引き起こす“時限爆弾”が成長しているのです。
清算が清算を呼ぶ仕組みは、株式市場には存在しない規模感でビットコインを揺さぶります。
2025 年 2 月 3 日、米中貿易摩擦をきっかけにビットコインが 5 分で 5% 下落しました。
この瞬間、デリバティブ市場では 2.2 billion USD 分のポジションが立て続けに清算され、70 万以上のトレーダーが一夜にして退場しました。
出典:CCN
同年 5 月 18 日の 106,000 USD 到達直後の急落でも 6.85 hundred million USD が吹き飛び、レバレッジ依存の危うさが改めて露呈しました。
出典:VOICE OF CRYPTO
清算規模が大きくなるほど、現物市場にも売り圧力が波及し、価格はスパイラル的に深掘ります。
こうして「借金で買ったビットコイン」は、ほんの数分で借金だけを残し、保有資産を蒸発させるのです。
証拠金維持率と強制清算のメカニズム
証拠金維持率とは、保有ポジションに対して最低限必要な担保の割合を示す指標です。
レバレッジ倍率が高いほど維持率は低く設定され、10 倍なら約 10%、100 倍なら約 1% 程度が一般的です。価格が逆行してポジション損失が担保を侵食し、維持率が規定値を割り込むと、取引所は強制ロスカットを実施します。
ロスカット自体は取引所の信用リスクを抑える安全装置ですが、市場全体を俯瞰すると「売りを強制する装置」です。
ロスカットが発動した価格帯は流動性が急速に枯渇し、さらに価格が下落しやすくなるため、連鎖清算(レバレッジ・カスケード)を生む温床となります。
個人投資家は「証拠金は失っても借金にはならない」と誤解しがちですが、滑りや大規模清算で想定以上に損失が膨らむと、取引所の規約に基づき追加証拠金の請求が届きます。
支払えなければ債務不履行となり、クレジットや法的責任の問題に発展するケースも少なくありません。
2025年清算イベントに見る急落リスク
2025 年 2 月の清算イベントは、ビットコイン市場の脆弱性を図らずも露呈しました。わずか 5 分の下落が引き金となり、その後の 1 分間で追加 8% の急落が発生しています。
総額 2.2 billion USD の清算が雪崩のように実行され、現物相場も短時間で 12% 以上の値下がりを記録しました。
清算規模が大きくなると、カウンターパーティ(逆側のポジション)を引き受けられる流動性プロバイダーが不足し、取引所は内部保険基金を取り崩すか、“ソーシャライズドロス”(損失の社会化)として他ユーザーの利益を差し引く場合があります。
これは本来勝っていたトレーダーにまで損失が波及する仕組みであり、レバレッジ依存市場の構造的リスクといえます。
同年 5 月 18 日の事例では、史上最高値を更新した直後に 15% の急落が発生しました。高値圏で建てたロングポジションの維持率は極端に低く、6.85 hundred million USD が短時間で吹き飛ぶ結果となりました。
「上昇トレンドの最中だから安全」と思い込んだ投資家ほど清算被害が大きく、FOMO とレバレッジの相乗効果が悲劇を拡大した典型例です。
レバレッジ心理と過大ポジション形成
「上がるときにレバレッジを掛ければ一気に資産倍増だ」と考えるのは自然ですが、心理学的には損失を受け入れにくい“プロスペクト理論”が働き、いざ損が出始めても「もう少し待てば戻るはず」とポジションを縮小できなくなります。
レバレッジ倍率が高いほど反発までの余裕は狭く、結果的に維持率割れまで自動的に突き進む構図ができあがります。
また、レバレッジをゲームの“スコア”のように扱う文化が SNS に根付いており、「100 倍で勝った」「10 倍は甘え」という投稿がバズを生むことも珍しくありません。
承認欲求が借金リスクを覆い隠し、過大ポジションを正当化する心理が強化されます。
借金を“レバレッジ”というカタカナに置き換えた瞬間、多くの人は負債のリアルな重みを忘れてしまいます。
しかし実際には、マイナス残高が発生すれば返済義務は回避できません。借入金には利息が付き、法的措置も現実に待っています。このギャップこそが、レバレッジ心理の最大の落とし穴です。
ビットコイン投資で元本割れが起きるプロセスと危険性
ビットコイン投資で元本割れが起きるプロセスや、それがどれほどリスクが高く危険なことなのか解説します。
- 半減期後の相場サイクルと急落要因
- ボラティリティの高さがもたらす元本割れ
- 伝統資産との比較で見る価格変動幅
半減期後の相場サイクルと急落要因
ビットコインは約 4 年ごとにマイニング報酬が半分になる“半減期”を迎えます。半減期後 1~1.5 年は供給減少を材料に強気相場になりやすいという経験則があり、2024~25 年の高騰もこのパターンに沿っていました。
ところが 2025 年 2 月の米中貿易摩擦は、半減期サイクルとは無関係に相場を急落させました。
供給面の論理だけで未来を予測できないにもかかわらず、投資家は「半減期後は上がるはず」という思い込みから高値掴みをしやすくなります。
ビットコインの半減期とは?なぜ価格が上がるのか、どう投資すれば儲かるか解説
借金で参入していた場合、こうした外生ショックに対する耐性は著しく低く、強制清算によって元本割れどころか負債転落へ一直線という結果になりがちです。
周期論はあくまで傾向であり、マクロ経済・規制動向・地政学リスクといった外部要因が上書きすることを忘れてはいけません。半減期サイクルに過度の信頼を置くことは、借金投資にとって致命的な誤算となり得ます。
ビットコインの今後の将来性については以下の記事で徹底解説しています。
ビットコイン(BTC)の今後はどうなる?2025年最新の現状・価格動向と将来性を解説
ボラティリティの高さがもたらす元本割れ
ビットコインの年率リターン標準偏差は、平常時でも 60% 前後に達する年が珍しくありません。
これは米国株(S&P500)の約 4 倍、金価格の約 5~6 倍に相当します。ボラティリティが高いほど、短期間で大きく下落する確率も高くなります。
レバレッジ 10 倍を掛けている場合、価格が 10% 下がるだけで証拠金全額が吹き飛びます。
ボラティリティ 60% という数字は、1標準偏差(統計的に 68% の確率で収まる範囲)でも 1 年で ±60%、1 週間単位でも ±15% 近い変動を意味します。10 倍ポジションではこの ±15% が ±150% に圧縮され、理論的には週内に破産水準へ達するリスクが常に潜むのです。
ボラティリティはリターンの源泉であると同時に、借金投資を瞬時に破綻へ導くトリガーです。
利息負担という時間的ハンデを抱えながら高ボラティリティ資産を保有するのは、長距離マラソンを鉛の靴で走るようなものであると認識する必要があります。
伝統資産との比較で見る価格変動幅
株式市場の信用取引は証券会社が厳格な追証基準を設け、倍率も 2~3 倍に制限されています。
一方、暗号資産取引所は倍率 100 倍以上を掲げ、維持率も極端に低く設定されています。
S&P500 の 1 日平均変動幅が 1~2% 程度であるのに対し、ビットコインは平常時でも 3~5%、イベント時には 10% を超えることが珍しくありません。
株と同じ 3 倍レバレッジでも、実効リスクはビットコインの方が概ね 3~4 倍高い計算になります。倍率を引き上げればその差は指数関数的に拡大し、100 倍ポジションでは 1% の逆行で“全損+負債”が発生します。
ビットコイン投資の借金・破産事例
ビットコイン投資で借金や破産してしまった事例を紹介します。
個人投資家の自己破産事例
英ガーディアン紙は 2023 年、英国在住のグラフィックデザイナー“ノア(仮名)”のケースを報じました。
彼は生活費を補うつもりでクレジットカードのキャッシングを利用し、レバレッジを掛けてビットコインを購入。価格が 30% 下落した時点で追証が発生し、最終的に約 £14,000 の負債を抱えて自己破産を申請しました。
ノア氏は「値上がり益で来月には返せる」と確信していましたが、急落は深夜帯に起こり、目覚めたときには取引所から残高不足通知が届いていたといいます。利息 18% のカードローンは、元本が減らないまま複利で増え続け、返済不能を早い段階で確定させました。
破産手続きでは暗号資産が財産とみなされるため、残っていたわずかな BTC も清算財産に組み込まれました。
結果、ノア氏の手元には“再起の種銭”がほとんど残らず、信用情報の回復にも長い年月を要することになりました。この事例は、「借金+高ボラティリティ」の組み合わせがどれほど再起を難しくするかを示す典型例です。
ビットコインで借金にならないための対策3選
- ポジションサイズと純資産比率の管理
- 分散投資によるヘッジをする
- 現物保有の長期投資にする
ポジションサイズと純資産比率の管理
最初に押さえるべきは「ポジションサイズ=命綱」という事実です。
一般に、金融工学の世界では 1 回のトレードで失ってよい金額は純資産の 1–2 % に留めるべきとされます。
これはケリー基準(勝率とリスクリターン比から最適賭け金を求める理論)が示す経験的上限に近い値で、資本を守りながら複利成長を狙う黄金比率とも呼ばれます。
借金付きレバレッジでは、この 1–2 % が「証拠金+借入元本+利息」の総合計に置き換わります。
たとえ証拠金だけをポジションサイズだと誤解しても、ロスカット後に残る債務は純資産比率を一気に引き上げてしまいます。
実務的には「ロスカットが発動し、なおかつ最大スリッページが起きた場合でも純資産の 5 % 以内で済むポジションか」を逆算することが、防御的にして最も合理的なチェックポイントとなります。
レバレッジ倍率の選定でも「最大ではなく最適」を軸に考えましょう。
統計上、ビットコインの日次変動が ±10 % を超えた日は年間 50 日前後あります。
10 倍レバでは一晩で元本超過損が常態化する計算であり、「安全運転」と言えるのは 2–3 倍が限界です。倍率を一段下げるだけで生存確率が数倍に跳ね上がる、これを肌感覚ではなく数値で把握することが、借金地獄に足を踏み入れない第一歩です。
分散投資によるヘッジをする
暗号資産は株式や債券と相関が低いと言われがちですが、急落時には“リスク資産”として一括りに売られ相関が急上昇する現象が確認されています。
そこで、短期債券や金(ゴールド)などディフェンシブ資産をポートフォリオの 20–30 % に組み入れ、下落局面で自動的にリバランス(資産配分の再調整)を行うと、ポートフォリオ全体のボラティリティを大幅に抑えられます。
統計値で示すと、2022–23 年の暗号冬において、BTC 単体の月次下落幅は最大 −37 % でしたが、BTC 50 %/米短期債 50 % の均等配分では −14 % で済んだというデータがあります。
現物保有の長期投資にする
ビットコインをレバレッジや借金でなく現物(スポット)で購入し、そのまま長期保有する戦略なら、最悪の場合でも損失は「保有価値がゼロになる」だけで済みます。
追加の追証(追加担保)を差し入れる必要もなく、マイナス残高が発生して借金を背負うリスクは本質的に存在しません。価格変動は避けられないものの、「ゼロ以下には落ちない」という明確な下限があることで、心理面の負担が大幅に軽減されます。
もう一つ大きな違いは、利息コストや返済スケジュールに縛られない点です。レバレッジ取引やローン購入では、時間の経過とともに利息が複利で積み上がり、含み益を圧迫します。
現物投資であれば保有期間が長くてもコストは保管手数料や取引所の最低維持料程度に限定され、時間そのものが味方になります。
結果として、短期の値動きに振り回されず、半減期サイクルや採用拡大など長期ファンダメンタルズに集中しやすくなります。
さらに、現物のみで組んだポートフォリオは強制ロスカットが発動しないため、「夜中に相場が急落して起きたら残高が消えていた」という最悪のシナリオを回避できます。
値下がり局面では一時的な含み損を抱えるものの、追加資金を投入しなければ負債は増えません。こうして守りに徹した長期保有を採用することで、市場の急変があっても生活資金や信用情報を毀損せずに済むのが、現物投資の最大の強みです。
長期投資を行う場合は、基本的に積立投資がおすすめです。「やめとけ」と言われることもありますが、その理由を含めておすすめな理由を解説しています。
ビットコインの積立投資はやめとけ?理由や失敗を招く罠などを解説
ビットコインの借金に関するよくある質問
- ビットコインのレバレッジは何倍までが安全?
- 借金での暗号資産購入は法的に問題ないのか?
- 元本割れした場合に取れる具体的な対処法は?
ビットコインのレバレッジは何倍までが安全?
「安全」という言葉は相場に絶対がない以上、あくまで統計的に許容しやすい水準を指します。伝統金融を基準にするなら 2–3 倍が上限と考えるのが現実的です。
なぜなら、ボラティリティが株式の 4 倍なら、同じリスクを取りたければ倍率はその 4 分の 1 が目安になるからです。
ただし、倍率だけでなくポジションサイズも同時に管理しなければ意味がありません。
純資産 100 万円の人が 3 万円を証拠金に 10 倍レバで 30 万円分のポジションを取る――実効倍率は 0.3 倍に過ぎず、リスクはむしろ低い場合もあります。
倍率と資産比率を掛け合わせた実効レバレッジこそが判断基準であり、これが 1 倍を超えない範囲に抑えるのが、損失耐性を高める最短ルートです。
借金での暗号資産購入は法的に問題ないのか?
多くの国では、個人が消費者ローンやクレジット枠を利用して暗号資産を購入する行為そのものは違法ではありません。
ただし、ローン契約には目的外使用を禁止する条項が含まれるケースがあり、虚偽申告が発覚すると契約違反として一括返済を求められるリスクがあります。
また、暗号資産の購入資金を担保に追加融資を受ける“二重借入”は、金融庁(日本)や SEC(米国)が「高リスク商品として投資家保護を強化すべき」と指摘してきました。
今後は規制強化でレバレッジ上限を引き下げたり、担保評価に厳しいヘアカット(安全マージン)を課す動きが加速すると見込まれます。
元本割れした場合に取れる具体的な対処法は?
- 追加担保の投入
- 損切り
- 債務整理専門家への早期相談
1番目の選択肢は「追加担保の投入」です。追証を納めればロスカットは回避できますが、これはリスク資産へのさらなる債務上乗せを意味します。
資金繰りに余裕があり、長期見通しが変わらないと確信できるときだけに限定しましょう。
2番目は損切りと債務整理を同時に行う方法です。含み損を確定させてポジションを閉じ、残った借金を低金利ローンやリボ払いから借り換え、返済スケジュールを組み直します。
損失の確定は痛みを伴うが、利息による持久戦より被害が限定される”という考え方です。
3番目は債務整理専門家への早期相談です。
自己破産や個人再生は最後の手段ですが、返済不能が視野に入った時点で弁護士や司法書士に相談すると、任意整理(利息カットと分割返済の再交渉)によって生活再建の糸口がつかめるケースも少なくありません。
時間が経つほど延滞金と利息は累積するため、「債務の雪だるま化」を止めるには早い段階で専門家にアクセスすることが決定的に重要です。